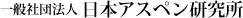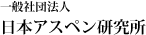「対話の文明」を求めて(前半)ロバート・ハッチンス
2020年03月12日アスペンセミナー
新たな時代を切り拓くリーダーシップの涵養にご関心のある皆様に、日本アスペン研究所が行ってきた活動や蓄積してきた文献のなかから、ご参考になりそうな文章・講話などをご紹介しているこのコーナー。前回の小林陽太郎氏による「今、何故、アスペンか」に続いてご紹介するのは、米国アスペン研究所発足のきっかけとなったスピーチ『「対話の文明」を求めて』です。
1949年、米国コロラド州アスペンで開催された「ゲーテ生誕200年祭」において、シカゴ大学総長のロバート・メイナード・ハッチンスが行ったスピーチが、聴衆に大きな感銘を与えました。
スピーチの前半では、「瑣末化」、「無教養な専門家による脅威」という言葉で、ハッチンスの危機感が語られます。彼は、どんな危機感を持っていたのでしょうか。そして、それらは70年後の現在において、解消されたのでしょうか。
「対話の文明」を求めて(前半)ロバート・メイナード・ハッチンス(1949年)
 Robert Maynard Hutchins University of Chicago Photographic Archive, [apf1-05034], Special Collections Research Center, University of Chicago Library
Robert Maynard Hutchins University of Chicago Photographic Archive, [apf1-05034], Special Collections Research Center, University of Chicago Library われわれの時代の特徴のうち、最も予期せざるものは、人の生き方において、あまねく瑣末化が行きわたっていることである。急速に拡大する知識は、われわれに勝利感や達成感を与えてくれるはずであった。芸術や科学の広がりは、それらが人のもつ最も高い力を使わしめるが故に、人を高みに導くはずであった。瑣末化は、目的意識のなさ、重要なものは何もないという感覚、そして信念の欠如に起因している。それは、われわれが読み、聞き、見るもの、興奮して取り組むもの、楽しむための数多くの金のかかるやり方のうちに、明らかに示されている。また、米国では、いずれにしろ特に重要なものは何もないのだから、全ての活動の重要性は同じようなものだ、という原則に依拠する教育制度のうちにも、明らかに瑣末化がみてとれる。かくて、教育は、瑣末なやり方を助長し、そして瑣末主義は自己増殖する。
急速に拡大する知識は、われわれに時間をもたらしたが、それは結局のところ浪費するためのものとなっている。今、われわれが享受している余暇(レジャー)は、ある意味で、人類の最高の獲得物である。われわれの先祖は、アダムの時代から、この遺産を残すべく苦心してきた。アリストテレスは、働くということは余暇(レジャー)のためである、と言った。働くということは、幾世代にもわたって、未だ生まれていない次世代の道を歩みやすくするためのものであった…が、その結果としてわれわれが勝ち得たものは何か? せいぜいコニー・アイランドではないか。
急速に拡大する知識は、専門化と実験によって手に入れられたものである。専門化の成功は、専門主義、すなわち教養や人と人との交流を断ち切るという代価を払って技術的訓練を志向する心的状態に導いた。さらに、専門主義によって、学者たちは、一般人との、いや他の学者との交流さえも妨げられているのである。
われわれの文明にとって最大の脅威は、無教養な専門家による脅威である。彼は、専門家であるという理由で敬意をはらわれる。彼の助言は、狭いながらも彼の専門性の高さの故に、専門でない分野についても耳を傾けられる。しかし、彼は他の分野のことは何も知らず、自分の専門分野との関係も知らない。彼は、したがって、自分の専攻以外の分野においては、ほとんど愚鈍な子供と同じなのである。
実証主義の成功は、実験によって得られた知識のみが確実な根拠をもつ、と信じ込ませるようになった。規範的な知識は、実証的に獲得できるものではないので、規範的な知識は存在し得ないことになる。社会科学や法は、それ故に、その倫理的な根拠を失い、記述的で統計的なものになってしまって、通常は、社会は力の組織であり、法は組織化された力の執行者がなすところのものである、という考え方を中心におくことになる。
芸術は、装飾的ではあっても、たいして重要なものとは見なされていない。自分自身の好みがわかっていれば、芸術に興味をもつ必要はないし、もちろん、それについて知る必要もない、とされる。実証的な科学が、自ら検証し得ないし、それ故に説明しようともしない原則もしくは大前提に依存しているにもかかわらず、哲学は迷信か、そうでなければ独断を体系的に述べたものだ、とみなされている。
巨大で、神秘的で、官僚的な増大する国家権力と、同様に巨大で、神秘的で、官僚的な企業の権力のゆえに、個々人が自分の生き方を自ら管理する力は、遠く離れた接近しがたい地点に追いやられてしまった。個人が一般的なシニシズムや無関心、瑣末主義に閉じこもってしまいたくなるのも、したがって故なしとしない。ゲーテは、いかなる状況も、行動と忍耐によって高尚にできる、と言った。彼は、真実に向けて努力するよう呼びかけた。しかし、もしも高尚というようなものがなければ、どうなるのか? もしも真実がなければ、どうなるのか? もしわれわれの人生に関する決定的な判断が、全て遠隔地の名前もない計算機によってはじき出されるとしたら、どこに苦労して行動したり忍耐する必要があるのだろうか?
同時に、われわれが所属する政治的、宗教的、経済的、社会的なグループは、いずれも、考えることを断念させたり、他のグループに属する人たちから切り離すよう圧力をかける。そして、どこに誰によって敷かれたか、わからないが、とにかく受け入れなければならない、そして当然他のイデオロギーとは相容れない路線に、疑問をもたずに順応するよう圧力をかけてくる。このような状況下では、現代人のシニシズムや無関心、瑣末主義は驚くにあたらない。このような状況下で、われわれが自由を、克己としてでなく、放縦のそれとして定義づけるとしても、不思議ではない。産業化というものは、あるいは少なくとも機械化というものは、逆転できないプロセスであることをわれわれは知っているし、もしできるとしても後戻りはさせないだろう。機械はわれわれに時間をもたらし、われわれはそれを余暇(レジャー)に変えることができる。レジャーにあたるギリシャ語は、学校(スクール)という言葉の起源であることを想起してみるのも有益であろう。ギリシャ人にとってレジャーは、彼らの最も高い力を磨くための、すなわち知的な活動、芸術の鑑賞、市民の義務としての行為のための機会であった。ゲーテの生涯は、この意味でレジャーの一生であった。ギリシャ人は、奴隷を所有することによって、レジャーを手に入れた。われわれはそうしようと思えば、機械を所有することによって、レジャーを手に入れることができる。われわれが時間をどう使うかは、意志の問題である。機械化が、われわれが今日知っているそのままの産業化の形になるか、あるいはそこで生まれた時間をわれわれ自身を高めるのでなく堕落するために使うかは、必ずしもあらかじめ定まっていることではない。

専門化の成功は否定しようもなく、決してそれを放棄すべきではない。われわれは専門化の果実である科学や技術、医学の長足の進歩なしにはやっていけないだろう。しかし、専門家というものは、専門的能力に対する誇りがあるからといって、無教養であったり、その専門性が求める以外の諸々の事柄に無知であったり、市民として人間として間抜けであったり、まさに文盲の農民より程度が悪かったりしていい理由があるだろうか? 大学教授たちが、クラブで、天気の話以外にはお互いに共通の話題がないというような事態は、止むを得ないことなのだろうか?
(後半につづく)