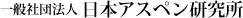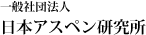村上陽一郎先生×猪木武徳先生 対談『教養としての「漱石」』(2)
2020年07月21日世界・日本
対談の冒頭では、知識人、教養人であった夏目漱石の姿に触れながら、教養とは何かについて、対話が交わされました。
「いかなるメディアを使っても自分の言いたいことがきちんと言えること」「相手の立場に身を置くとか、自分を省みて見るというような自省的な態度、謙虚さ、日常的でないものにぶつかったときに応用のきく精神の柔らかさが、本当の意味での教養」ではないかといった両先生のご指摘は、教養ブームの真っただ中の現在、「何のための教養なのか」ということを、改めて考えさせられます。
対談は、さらに漱石の女性の描き方や、知的バイタリティーについてと展開していきます。一人の作家に対する多様な観察。ここに繰り広げられる対話の醍醐味をご堪能ください。
猪木武徳・国際日本文化研究センター教授
村上陽一郎・国際基督教大学教授
(司会)篠原 興・㈶国際通貨研究所顧問
(いずれも、当時のお肩書)
知識が増えると謎も増える

篠原:猪木先生のご本によると、一つの問いには必ず一つの正しい答えがあるという西欧風のものの考え方は絶対的なものに対する憧れを生み出しやすく、行き着く先は進んだ西洋にすべての民族が近づくのが進歩であり、遠いほど異端であるという発想になると。しかし、そうではなく答えは無数にあると言うと、今度は完壁な相対主義とその先にあるニヒリズムに陥る危険があるので、そのどちらでもない共通価値というものをどうやって自分のものにし、どうやってみんなと共有するか。この二つについて考えることが、教養そのものなのではないかという気がしますが。
村上:例えば相手の立場に立つためには、まず自分をある程度客観視できなくてはいけない。自分の立場は何なのか、いま自分が立っているのはどこかを見つめないといけないわけです。先ほどの自省的な態度ですね。リフレックシプ(reflexive)という英語が一番ぴったりくると思いますが、そういう発想がなくてはいけない。多元的にさまざまな領域の考え方を少しずつ学ぶというのも、そこへ行くための一つの手順としてあるわけです。ですから、最初から専門に取り込まれてしまって、「一所懸命」という言葉のように一つのところに命をかけると言ってしまった瞬間に柔軟性は失われていく可能性があるので、やはりいろいろなところに身を置いてみる体験を若いうちにしておくのは、教養のための一つの手順として大事なのではないかと思いますね。
漱石は、学者としては英文学を専攻していたわけですが、彼の学問的素養の中には、漢学についてのものすごく深くて広い知識がある。猪木さんはどうかわかりませんが、私など漢詩を書くことはほとんと不可能です。
猪木:私も全く不可能です(笑)。
村上:でも漱石は、さらさらっと五言絶句などを簡単に詠んだ。あのころの人たちは、まだ普通に漢詩をつくれたんですね。そうかと思えば、見事な英詩も書いています。そしてあの時代、当時の日本人たちが文明開化で西欧一辺倒だったのに対して、彼は西欧ぞっこんにはならなかったし、伝統的な武士道だの儒教だのにも戻りませんでした。つまり漱石は、いくつもの観点と立場を自らの中に見出せる人だったのではないでしょうか。
ただ俗に言われてきたことですが、漱石は女性を描くことがあまり上手くないということはあるかもしれませんけどね。
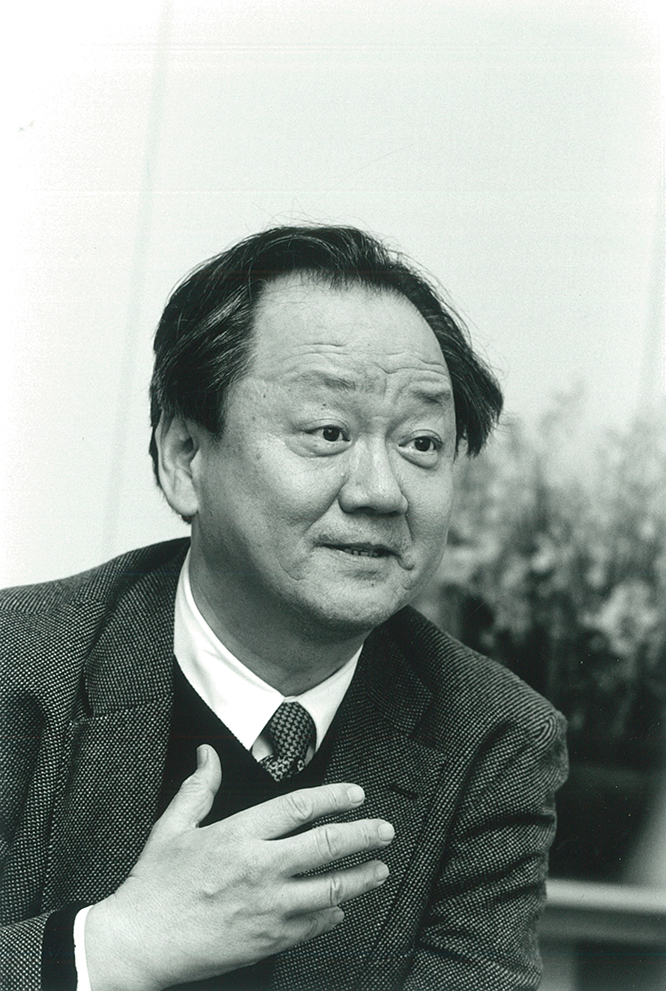
猪木:その点に関しては、ちょっと私、意見があるんですよ(笑)。おっしゃるように漱石の作品には、無口で頑固なところがあったり、不可思議な笑みを浮かべたりと、正体のはっきり把握しにくい女性が少なからず出てきます。そして、漱石の小説には家庭内の夫と妻の間の微妙な情感を描いたものが多いですね。しかも意外に女性は気が強くて従順ではなく、何かを心の中にため込んでいるという感じです。これは、私の専門の社会科学的な見方に引きつけ過ぎる解釈かもしれませんが、近代化の進んだ20世紀初頭には人間は個々ばらばらになり、さまざまなしがらみから解放されて自由を謳歌する半面、孤独の寂しさから逃れることはできなくなった。漱石は『こころ』の中で「先生」にそれを言わせていますね。家庭という最小の社会的な単位で、人間同士の最も情愛にあふれる夫婦の間でも、よく見てみるとやはり微妙な断絶が生じている。それを描こうとしたからこそ、漱石は意図的に下手に女性を描いたのではないか(笑)。近代とは、まさに情感をお互いに理解することができない状況を生み出した時代なんですね。
それから、漱石は漢詩も英詰も書いたし、チェーホフもイプセンも英語で読んだでしょう。つまり当時の世界文学をたくさん読み、いろいろな創作活動を行っている。それは専門家として専門だけを知っているということに対して疑問があったからだろうと思います。旧約聖書などに登場する人物を見ても、やはりいろいろな能力を持ち、一つのことだけに詳しいというような人間はいませんね。いろいろなことに関心を持って外に向かって活動するような、そういう知的バイタリティーにあふれている。ですから、何か一つのことを深く掘り下げながら獲得する知識も重要かもしれませんが、人間の知的な能力とはそういうものではないという思いを密かに持っているんです。
フランスにアランという哲学者がいますね。彼は「人間は知りたいと思って知識を増やしていく。それを球体に例えると、知識がどんどん膨らんでいくに従い、未知の分野はどんどん狭くなると考えがちだ。しかしそうではなくて、実は球体が膨らむと表面積も増え、人間が知りたいことや疑問などは表面が外の世界と接するところから生まれてくるから、知識が増えると新しい疑問もどんどん増えてしまう」と言うんです。つまり、専門を掘り下げていくと、わからないことがどんどん少なくなると思われがちですが、本当に優れた専門家はそうは言わないわけですね。
村上:多分そうでしょう。いま格闘している問題が解決したとしても、必ずその先にまた扉が一つある。その扉を開けると、その先にまた扉がと、それは永久に続くんだと専門家でもそう考えている人はいます。でも扉の比喩は二次元的な動き方ですが、球体の表面積は三次元的に増えるわけですから、疑問の増え方ははるかに多いですね。
最近、評論家の三浦雅士さんが『出生の秘密』(講談社)という力作を書かれていて、その中で漱石がかなりの部分を占めているんです。それによると漱石は、生まれてすぐに養子に出され、また実家へ戻ってと不安定な子ども時代を過ごしている。それが彼の作品の中に反映されているわけですが、三浦さんは執拗に奥さんの鏡子さんとの関係を追い詰めていくんです。それを読むと、先ほど猪木さんがおっしゃったような女性の描き方における目論見も確かにあったと思いますが、同時に実生活での鏡子さんとの葛藤が、彼の女性に対する描き方のややシニカルなところに投影されているのかもしれないという気もします。
次回へ続く