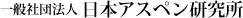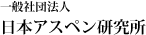関根清三先生の「人文学不要論に寄せて―セミナーの現場から(2)」
2020年10月30日古典
前回のコラムで関根先生は、猪木武徳先生やヌスバウム女史を引用しながら、人文学は権威主義に対抗するための「クリティークの精神」と、多様な他者に対する涵養さと忍耐を培う「イマジネイション」を陶冶するのに不可欠だとの指摘をされました。
今回のコラムでは、アスペン・セミナーのテキストを題材に、「クリティークの精神」と「イマジネイション」が養われていく様が再現されます。実際のセミナーでどのような対話がなされるのか、多少ネタバレも含まれますが、そこは、正解がないのが「アスペン式対話」。多様な読み方のひとつの例と捉えていただき、自らのクリティークの精神とイマジネイションを培っていく際のご参考にしていただければと思います。
Ⅱ.アスペン・セミナーの現場――テクスト読解の実例
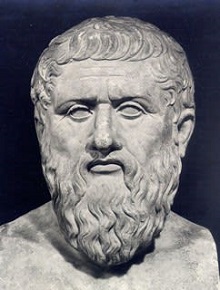
まずプラトン『ソクラテスの弁明』から。ソクラテスは、彼より賢い人間はいないという神託の正当性を疑った。そこで政治家等、世のリーダーたちを訪ね対話をした結果、確かに自分が無知であることを自覚している点において、彼らより少しだけ賢いことに気付いたという。モデレーターはふつう参加者に向かって、次のような投げ掛けをする。「無知の知と言うけれども、ソクラテスだって色々なことを知っているではないか。政治家は政治について、詩人は詩について、手工者は技術について知っている。では無知とは何についての無知なのか」と。その答えは、政治家訪問のくだりの、「我々は善についても美についても何も知っていまい」という箇所にある。人は善美といった重要な事柄について、何が善美か、その例は知っていても、何故それが善美と言えるのか、体系的に根拠づけることができない、その意味で無知なのだ。それなのにリーダーたちが、自分の専門について知識を持っているからと言って、善美の事柄についても知っているかに勘違いし、勝手なことを言い権威を纏っている社会、それは危ない。そうした危機感に駆られてソクラテスは街頭で人々と哲学的な議論をし、彼一流の問答法によって、無知の知の認識に至ることを促した。人文学、特にソクラテス以来の哲学は、こうした権威に対する率直な疑念・クリティークの精神を擁して、問答・対話を重視する。それがアスペンの大事な方法となっているわけである。そのことの重さを、我々は繰り返し想い起こす必要があるに違いない。
なお『ソクラテスの弁明』や『ラケス』『プラタゴラス』篇などで、哲学は《魂の世話》という定義が出て来る。人は体の世話はするけれど、魂の世話は怠りがちだ。しかし自覚的に魂の世話をするのが哲学である。アスペンはそういう魂の世話をする場なのだということに、セミナーのどこかで触れておくことも、この論脈でまた必要な筈である。

さて、西のソクラテスより約1世紀前の東の思想家、孔子の『論語』にもクリティークの精神は横溢している。学而篇の「子曰、君子不重則不威、學則不固、主忠信、無友不如己者、過則勿憚改」もその例だが、これについてはしばしば、参加者からのクリティークも提出される。7月のセミナーでも、「己れに如かざる者を友とすること無かれ」というのは、随分利己的な友人観だという批判が相継いだ。モデレーターとしては批判がひとしきり出そろうまで待った後おもむろに、そもそもこの漢文の訓読の仕方は正しいのかという揺さぶりをかけた。「無友不如己者」はむしろ「友に、己れに如かざる者、無し」と読むべきではないか。これなら、友はみんな自分より優っていて、友人から学ぶんだという謙虚な姿勢を言っていることになり、孔子の思想にも相応しいだろう。これは実は松山幸雄先生に教えていただいた説だが、解釈史を調べてみると、有力な読み方として支持されている。セミナーでは、この一句の議論はこの辺りで収束して、次のテーマへと移って行ったけれども、実は後日談があった。漢文に関心の深い参加者がおられ、北海道大学の中国哲学の教授が友人ということで、セッションのあと早速メールで問い合わせ、これは有力な説だとお墨付きをもらった。そのことを翌日のセッションで報告してくださったのである。こういう知的好奇心の豊かな参加者がおられると、われわれも刺激を受け、モデレーター冥利に尽きる。

以上2編はエグゼクティブ・セミナーで採用されている哲学畑のテクストだったが、次にヤング・エグゼクティブ・セミナーのテクストから、しかも文学作品を見てみよう。ドイツ時代の恋人が訪ねてきたのに冷たく追い返す中年の官吏・渡辺参事官の姿を描いた、森鷗外「普請中」である。
渡辺に侮辱された思いで、「凝り固まつたやうな微笑を顔に見せて、黙つてシヤンパニエの杯を上げた女の手は、人には知れぬ程、顫つてゐた。…ヴェエルに深く面を包んだ女を載せた、一輛の寂しい車が芝の方へ駈けて行つた」、とこの小説は結ばれる。この寂しさは、女の寂しさを鷗外が想像しているだけでなく、渡辺の寂しさをも想像した一句なのか否か。あるいは、そもそも作者・鷗外自身の心中はどうなのか。読者は、様々にイマジネイションを働かせることを強いられる、そういう小説である。
幾つかの読み筋があるに違いない。
1つは、鷗外は非常に冷たい男で、モトカノに対してこういう仕打ちをしても何とも思わなかったのだという読み筋。実際、この20年前に書かれた『舞姫』の末尾も、恋人エリスを妊娠発狂させながら、涙金を母親に渡して帰国する冷淡な男を描いている。だから、この読み方を全く排除することはできない。しかし、エリスのモデルになった女性が来日した折り、一等船客として優雅な船旅をし、高級ホテルに泊まっていたことが、最近の鴎外研究で突き止められている。貧しい舞姫などではなく、下宿先の裕福なお嬢さんだったらしく、妊娠も発狂もしていなかった。あの舞姫の結びは、するとフィクションであって、それとの類比で「普請中」にも冷淡な鷗外像を読むのは、単純すぎるかもしれない。
とすると、第二の読み筋が浮かび上がってくる。すなわち、鷗外はかなり偽悪的あるいは自己批判的な人で、ドイツでの恋愛を成就できなかった自分を鞭打っているのだと。下手をすれば相手を妊娠発狂させた可能性もあったけれど、たまたまそこに至らなかっただけで、自分は本当は悪い男であり、その俗物のなれの果てがこの渡辺なのだと、鷗外自身、それこそイマジネイションを駆使して自分を罰している可能性があるかもしれない。第一の読みが、女性を傷つけていることに気づかない想像力ゼロの男という鷗外像なのに対し、第二の読みは、むしろ非常に想像力が豊かで、また良心も鋭い男という鷗外像となる。
ただ、何も鷗外を徒に美化して話を丸く収める必要もないので、第三の読み筋も付け加えておくならば、この小説と同時期に発表された、「予が立場」という文章が注目される。ここで鷗外は、レジグナシオーン(諦念)が自分の立場だと語っているのだ。とすると、文字通り「普請中」の日本のために、陸軍軍医・官僚として身を捧げ、私的な恋愛については諦めた明治の男の姿勢を、それ以上でもなくそれ以下でもなく淡々と描いたのが、この小説だという読みも出て来る筈である。つまり、「一輛の寂しい車が芝の方へ駈けて行つた」という結びの一句も、ドイツ女性の寂しさだけでなく、渡辺参事官、そして鷗外自身の寂しさも暗示している。我々はそこまでイマジネイションを働かせることを促されるのではないか。
これ以外にも色々な読解の可能性があるが、それらのいずれの読みを正解と決する決め手はないだろう。こうした読みの幾つかが、セッションの対話で出て来ることもあれば、そこまでいかないこともある。いずれにせよ、大体こういった幾つかの読みへとイマジネイションを働かせ、その何れを取るかは参加者に委ねてセッションを閉じる。私はそのようなモデレーションを心がけており、9月のセミナーの議論も大体その方向だった。確かに「普請中」は一読してちょっと後味の悪い小説だけれども、人文知のイマジネイションを働かせる練習には好適のテクストだと思われる。
(次回に続く)