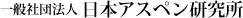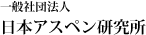塩川徹也先生「文学は何の役に立つのか(2)」
2021年01月25日ヒューマニティ
塩川先生は前回のコラムにおいて、文学が現代人にとってどのように役立っているのかについて考える手始めとして、「文学」という語の定義を東西の歴史にさかのぼって語られました。もともと「文学」あるいは“literature”という語には、中国においても西洋においても、「言語表現による芸術作品」という現代通用している意味よりも、「学問一般についての深い知識、学識」といった意味で解されていたとのことです。
今回のコラムでは、そうした「文学」という語の理解のもと、それが教育の中にどのように組み込まれていたのか、さらには、それが何語によって教えられたのかについて、考察を進めます。
塩川先生は、この考察の中で、「母語」に対する「父語」というタームを提唱されます。果たして、「父語」というタームには、どのような意味合いが込められているのでしょうか。

*
以上の意味での文学は教育の中で、いかなる位置を占め、いかなる役割を果たしていたのでしょうか。それは、少なくともかつてのフランスにおいては、humanités(英語の humanities)あるいは lettres (=letters) の学級(クラス)と呼ばれて、中等教育の根幹をなしていました。それは文字の読み書きと文法の学習から始まってレトリック(弁論術)、つまり公共の場において聴衆・読者を説得するための弁論を準備して実践する技術の習得に至る教育課程でした。ただし哲学はヒューマニティーズに含まれません。哲学は一般教育の総仕上げとして、中等教育の最終学年あるいは大学の専門学部の予備課程で学ばれることになっていました。ここで言う哲学は、もちろん今日の文学部等で教えられる専門科目としての哲学ではありません。法律や医学や神学といった職業に結びつく専門的学問を学ぶことになるエリートたちが、専門に分化する前に身につけるべき一般教養のことだったのです。
哲学が専門教育の手前にあって一般教育・教養教育の中核をなすとすれば、ヒューマニティーズないし文学はさらにその手前にあって、ことばの教育に関わります。それは文字の読み書きとテクストの読解力を養成することを通じて、あらゆる分野の学問を学ぶことを可能にします。洋の東西を問わず、読み書きの能力としてのリテラシーはすべての学問のプラットフォームなのです。しかしヒューマニティーズにおけることばの教育はそれだけにとどまりません。ヒューマニティーズは、狭い身内の輪を超えて、職場、一般社会、さらには公共の場において、利害関心を必ずしも共有しない他者とコミュニケーションをとるためのことばの使い方、いわば言語の公共的使用を教えます。ヨーロッパの伝統的な中等教育の根幹であったレトリックの目標はここにあります。
*
ところでヒューマニティーズの学級で教えられることばは、何語なのでしょうか。ヒューマニティーズには、古代ギリシャ・ローマの言語・文学の研究という意味もありますから、古典語、とりわけラテン語が頭に浮かびます。ラテン語は中世ヨーロッパの共通語だったのですから、それは間違いではありません。しかし近代になってヨーロッパの先進地域で国民国家の形成が進むにつれて、重点は自国の公用語に置かれることになります。要するにイギリスなら英語、フランスならフランス語ということです。ヒューマニティーズの教室で、生徒たちは自国のことばの読解力と運用能力を磨いたのです。しかしどうして生徒たちは、自国のことば、つまり母語ないし母国語を学校で時間をかけて学ばなければならなかったのでしょうか。
母語(英語の mother tongue)という言い回しには注意が必要です。母語というと、私たちは自分の国のことば、日本人にとっての日本語、アメリカ人にとっての英語を思い浮かべ、母語の反対語といえば、外国語のことを考えがちです。しかしこのような理解の仕方はミスリーディングです。母語は、母親に代表される家族や近隣によって口移しで教えられることば、基本的には話しことばで狭い地域にしか通用しない言語と考えなければなりません。そうだとすれば、子供が成長して大人になり、身内ではない他者と関係を取り結び、社会生活、職業生活、公共生活をきちんと営んで行くためには、文字に基づくより高度な言語を習得しなければなりません。それを教えたのが、かつてのヨーロッパではヒューマニティーズであり、現代の公教育では、日本なら国語、英語圏であれば英語(English)、フランス語圏であればフランス語(français)という教科なのです。
それでは、それらの教科で教えられる国語、英語、フランス語――念のために言えば、それらの教科は原則として native speaker を対象としています――は、生徒にとっていかなる言語なのでしょうか。それが母語と言えないことは、もうお分かりいただけると思います。実は、学校で教授される自分の国ないし地域のことばを適切に指し示すタームはありません。それをいいことにして、勝手な言葉遣いをお許しいただければ、それは「父語」つまり父親のことばです。母語が幼少期に耳と口を通じて自然に習得する言語だとすれば、父語は眼と手を使って文字を読み書きする訓練を通じて身につけていく言語であり、教育という人為に属する事柄です。言い換えれば、父語は自然に習得できるものではないのです。私たちは、外国語の学習が問題になると、母国語のほうはすでに自然に習得していて学ぶ必要がないと思いがちですが、それは錯覚です。今日の世界では、日本の子供もアメリカの子供もフランスの子供も、それぞれ父のことばとしての日本語、英語、フランス語を義務教育の課程で習得します。それによってはじめて社会生活と職業生活を円滑に送ることができるようになるのです。そのような教育課程がかつてヒューマニティーズないし文学(letters)と呼ばれていたとしたら、そして文学の使命の一つがリテラシーの養成にあるとすれば、文学が他者とともに社会の中で生きる一人一人の人間にとって役に立つのは明らかではないでしょうか。
(次回に続く)