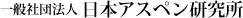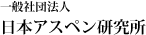東日本大震災から10年 震災後の鼎談を振り返る(2)
2021年04月05日科学・技術
東日本大震災一年後の会報「アスペン・フェロー」に掲載された鼎談。
鼎談の冒頭で村上先生は、大震災で明らかになった技術と倫理に関する問題として、本来、”engineering”という概念に含まれていたはずの現場と直結した「行動規範」の意識が日本の「工学」で欠落してしまったこと、技術を社会に応用する際、ステークホルダーを巻き込んで行うテクノロジー・アセスメントが、開発の上流どころか下流でしか行われていなかったことが専門家と社会の間に乖離を生んでしまったことを指摘されました。
鼎談の続きでは、関根清三先生から、リスクマネジメントにおいて「間違った確率論の適用がどうして生じたのか」という問題が提起されます。そしてそこには、確率論の問題だけではなく、根深いコミュニケーションの問題が横たわっていることが明らかにされていきます。
大震災から10年たった現在も日本社会が抱え続ける、コミュニケーションという本質的な問題を、皆さんはどうお考えになるでしょうか。
村上陽一郎
●日本アスペン研究所副理事長
東洋英和女学院大学学長
関根清三
●日本アスペン研究所諮問委員
東京大学大学院人文社会系研究科教授
荻野弘之
●上智大学文学部哲学科教授
〈司会〉
山口裕視
●国土交通省総合政策局国際政策課長
(※肩書は当時)

関根 村上先生は専門家グループのリーダーとして人知れぬご苦労がおありだったと存じます。私はまったくの非専門家ですが、多くの読者が感じている疑問だと思いますので、この機会に確率論的安全性の問題について教えていただきたいと思います。原発の冷却装置が主電源で動かなくなる確率も予備電源で動かなくなる確率も共に1万分の1だから、両方が駄目になる可能性は両者を掛けた1億分の1で、ほとんどゼロに等しい、だから原発は安全だと言われてきました。しかし実際には主電源も予備電源も同じ津波で駄目になったわけで、リスクは1万分の1でしかなかった(加藤尚武『災害論』)。こうした間違った確率論の適用がどうして生じたのでしょうか。
村上 日本の原子力の世界では、リスクマネジメントを公的に議論することが社会的に許されない雰囲気がずっとありました。原発大国と言われるフランスでは、もう随分前から原発周辺の小学校で一年に数回、いろいろな状況を設定して避難訓練を行ってきました。いまは日本でも避難訓練をするようになりましたが、以前はそういうことを言い出すだけで、だから原子力は危険だ、手を出すべきじゃないと非難されるのが日本の社会でした。私は2003年に『安全学の現在』を書き、そうした雰囲気を何とか壊そうとしてきましたが、実際に「リスク」という言葉を原子力の世界で言えるようになったのは、ここ二十年ぐらいです。安全神話が壊れた、と言うけれど、技術の世界ではもともと「絶対安全」などはあり得ない。リスクを言い立てられないような社会の側にも問題があったはずです。
その上、リスク評価の基本である確率を使うこと自体が、社会になじまないという厄介な問題があるんですね。例えば某組織の長が、今回は一千年に一度の災害だから、続けて起こる確率はゼロに近い(だから原発の再開は問題がない)という言い方をしてさんざん叩かれましたが、一方から言えば「確率がゼロに近い」ことは「まず起こらない」それが起こる確率は認めなければいけないということですね。「まず起こらない」と判断してよいと同時に、しかし「絶対に起こらないわけではない」ことも伝えなければならないわけです。
それにしても確率というのは厄介ですね。なぜなら確率は意思決定のときの心理には影響を与えるにしても、結果の選択には役立たないからです。降水確率が60%だからといって、傘を60%だけ持っていくわけにはいきませんね。傘を持っていくか持っていかないか、どちらかでしかない。つまりシングル・イベント(単一事象)に対して確率というのは意味がない。それでも確率に頼って議論をする以外にない世界があるんです。
関根 目を将来に向けると、世代間倫理の問題も出てきますね。放射性廃棄物の有害性は千年持続するので、埋蔵処理された廃棄物は千年先までの安全性が担保されなければならない。ところが千年先の安全性の実験はできないのだから、リスクの受益者負担の原則からして、現世代は未来世代にこのリスクを押し付けてはならないのではないかといった問題。この点についてはいかがでしょうか。
村上 廃棄物の保管と処理は非常に大きな問題であることは間違いないと思います。ただ、国際的にさまざまな協定を結んで合意ができれば、私は地球の上で現在の放射性物質を保管する技術はあり得ると思っています。ただしそこには幾つもクリアしなければならない条件がありますが。
山口 その条件は、リスクマネジメントがタブーになってしまうような風潮をどのように克服していくかにかかってくると思いますが。
村上 そういう意味では、科学技術コミュニケ一夕ーの養成というのもひとつの解決策ではないかと思います。これは、基本的には非専門家の抱いている恐れや疑い、何か気持ちが悪いとか、そういう曖昧なことをきちんと専門家に伝えることができる能力、そして専門家の言葉を非専門家がきちんとわかるような方法でコミュニケートする能力、この二つの双方向的能力を備えたコミュニケ一夕ーを養成するための計画は、実はもう始まっているんです。震災以前の、昨年までの五年間に北海道大学と早稲田大学と東京大学とに三つの拠点をつくったんです。その他にも科学博物館や未来館でも独自に育成をしています。
関根 いま村上先生がおっしゃったことを言い換えると、テクノファシズムでもテクノポピュリズムでも駄目で、その間を埋めるものとしてコミュニケ一夕ーが必要だということですね。3.11以降、どのようにして合理的で民主的な判断システムをつくるかが喫緊事ですが、大変重要な示唆をいただいたと思います。
荻野 コーディネーター的役割がなかなか確立できないのは、日本の固有の文化や社会のあり方が背景にあるのかもしれません。立場が違う人たちがお互いに対話を重ねていく作法や心得が醸成できていないんですね。そこがうまくできれば、科学にしても政治にしても、いろいろなところで潤滑油となり物事が進むと思います。

村上 いま北海道でGMOをめぐる条例の改訂版が議論されており、絶対反対という人と推進派との間をどう取り持つかで北海道大学農学部の教授が苦労されているのですが、その議論の場で印象に残ることがありました。推進派の人が、反対派は感情的にただ批判だけしているどうしようもない連中だと思いながら、そんなことは顔に出せないのでひたすら誠実に対応しているつもりで話をしていて、もしかしたらこの人たちなりに北海道の農業のことを考えているのかもしれないと頭の中でチラッと思ったら、対話の結果がまるで違ったというのです。同様に反対派も、あの連中はモンサント社の回し者だと思っている段階では対話は成立しなかったけれど、賛成派も北海道の農業を何とかしようと考えているんだと考えると、コンセンサスが成立するわけではないけれど、対話が成立するようになったと。本当に人間って不思議なものだと思います。
荻野 村上先生の論点につけ加えると、対話というのは話をしている当事者だけの問題ではなく、むしろそれを聞いている人たちにとって大きな影響がある。我々もいまこうやってしゃべっているけれども、本当に誰に向けて語りたいかと言ったら、これを読んでいる読者ですね。つまり対話の当事者以外のところで説得や理解が生まれているか、対話のコンテクストの内と外がリンクしていることが重要です。だからテレビの討論番組のように口汚く相手を言い負かすというのではなく、もう少し上質な場をつくって見せていければ、対話をうまく回していくことにつながるのではないか。今回の震災でいろいろな問題が起こりましたが、それらが対話を阻害している日本の文化に風穴をあける機会になるかもしれないという期待を持っているんです。
村上 日本のエネルギー戦略をどのように考えるかというところで、やや抽象的なレベルですが良質な対話をつくり上げていこうという試みは始まっています。ただ「反対」と言っているだけではどうにも動かないという意識は人々の間に醸成されてきていて、私もわずかでもモラルサポートができないか、一所懸命やっているのですが。
関根 公正な専門家ないしコミュニケ一夕ーをどう選出するか、またどれだけの非専門家がそれに参加して正しく理解できるか。課題は多いでしょうが、重要な試みですね。
山口 専門家と非専門家をつなぐ対話の基礎となるようなもの、先ほど村上先生が共有できるものがあれば対話の結果も違ってくるとおっしゃいましたが、それが原子力では何に当たるのだろうかというのは、ちょっとまだ整理できないのですが。
村上 確かに時間はかかるでしょうね。
(次回に続く)